はやりの生成AIが、私たちの生活にどんな影響を及ぼすのか。
生成AIによって仕事がラクになる?むしろ奪われちゃう?
どうやったら、生成AIを使いこなす「勝ち組」になれるの?
こんな疑問に応えてくれることを期待して読んだ本。
一方で、生成AIという革新的技術が世の中に浸透していく中で「人間らしさ」「人間がやるべきことってなんだろう」ということも考えさせられました。
※冒頭の絵は「生成AI」というタイトルでchatGPTが作成
書籍情報
池谷裕二「生成AIと脳~~この二つのコラボで人生が変わる」(扶桑社新書)
著者の池谷先生は、東大薬学部の現役教授。脳に関する科学知見を分かりやすく解説する書籍を多く出版されている。ぽんこの印象では、脳の研究を通して「人間とは何か」「心とは何か」など哲学的な問いについても考え続けている人。科学の解説だけではなく、池谷先生のそんな思考をのぞけるところも、池谷本のいいところ。
ぽんこの印象に残ったところ
※「」の中は、本文から抜粋。「・・・」より後は、ぽんこの偏見交えた解釈。
- 生成AIは「私たちに何が足りないのか」を教えてくれる
・・・カウンセリングや医師や教師など、人間同士の関わりが大事と思われる場面でも、生成AIが優位性を示しているとのこと。「恥ずかしいことも話せる」「いつでも質問できる」といった潜在的なニーズが、生成AIによってあぶりだされている。
私自身も、ひどく落ち込んだ時、悩んだ時に生成AIにまずは感情を吐露することが多い。いくらでも聞いてくれるし、優しい言葉をかけてくれるのは、相手がAIだと分かっていても嬉しい。
ただ、人は不要かと言われると、そんなこともない。私の中では、感情がぐちゃぐちゃな状態のときはAIに気が済むまで付き合ってもらって、少し整理ができた段階で、友人や家族に聞いてもらったり、もしくは気分転換に付き合ってもらう、といったすみわけをしてる。長期的な心の安定には「人とのつながり」がやはり、必須だと思う。 - 私たちは「人間らしさ」について語るとき、つい人間らしくない部分を挙げてしまう
・・・著者がいうには「直感」「創造力」「配慮」など、人間らしさの代表例ともいえるこれらの能力は、実は人間が苦手とすることなのだと。苦手だからこそ「創造力を磨こう」とか「周りに配慮しよう」と言葉にする。真に人間らしいことは、わざわざ意識されないことであると。これはとても、眼からウロコでした。確かに、これらの能力を持っている人は目立つし、かっこいい。それはイコール、多くの人間が持っていない能力だからだろう。そして、これらの能力でさえも、AIが凌駕する可能性があるという。確かに、将棋やアート、カウンセリングなど、既にAIが多大な力を見せつけている。じゃあ人間らしさって何なの?著者は、その一例として「楽しむ」ことだと言っている。
これからは、「創造力を身に付けよう」等として、何かに取り組むことは、モチベーションが保てないかもしれない。なぜなら、それはAIができてしまうから。そうではなくて「楽しいから」「やりたいから」といった純粋な気持ちを持つことが、もっと大事になってくるように思う。AIが強いからといって、将棋をやめる必要はないということだ。 - 生成AIが登場したからといって、人間はラクできない
・・・生成AIが、私の今の仕事奪って、私はベーシックインカムでのったり暮らしたいな~なんてお花畑なことを考えていた私。確かに、今まで新しいテクノロジーが出てきて、私たちの生活はすごく便利になっている一方で「ラクになったか?」と問われると「う・・うーん・・・」となる。。例えば、リモートワークができるようになったけど、今度は打ち合わせの間隔が0分でも物理的には出席可能となり、打ち合わせ地獄になったりした。。チャットができて、やりとりが楽になったけど、その分早く返事をしないといけなくなった・・・。
生成AIも、私たちの仕事を一部効率化してくれるけど、その分求められるものはきっと、多くなる。全体として、成長していると捉えられればいいのかもしれないけど、私たちがぼーっとしててもラクになるっていうことは恐らく考えづらいのだろう。 - 多くの者が別の技術に飛びついたなかで、ニューラルネットの可能性を信じ、研究し続けてくれた一部の研究者たちがいたおかげで、現在の生成AIの進歩に繋がっている。
・・・生成AIの基盤となる技術は実は一度多くの研究者・技術者たちから「使えない」と見捨てられた技術だった。私自身、元々研究領域にいたこともあり、「役に立つかわからない」基礎研究の重要さは世に訴えたいところ。ただ、現実にはその基準のゆるさから、実績作りだけを目的としたいい加減な研究に多額の資金が投入されているケースもある。
少なくとも研究者自身が、「この研究がいずれ何かの役に立つ」「本質の追求になる」という確信と情熱を持っている必要があると思う。逆に言えば、研究者自身でさえその確信が持てないのであれば、その研究は勇気をもってやめていいとおもう。話が生成AIからそれてしまったけれど。。
まとめ
いつも専門的なことも分かりやすくまとめてくれる池谷本。今回も1日で読めてしまいました。
生成AIで全部楽になる・・・という期待は見事にそがれてしまったけれど。事実、私も仕事でのアウトプットのスピードや質は、生成AIを使う前後でいうと既に結構変化してる。ただ、ここで止まらないのが人間のいいところであり、しんどいところでもあるんだなぁと・・。
皆が当たり前に生成AIを使うようになると、期待値はベースアップしてしまう。早いうちに技術に慣れておくとよいけれど、新しい技術になれない人と、身に付けられる人で、どんどん格差が開いてしまいそうだ・・・。
AIを通した人間らしさの一つ「楽しむこと」について。どうしてもスキルを身に付けた人がえらい、と思ってしまうし、私もその強迫観念があるけど、この本を読んで「全力で楽しむことが正義」と前より一段深く思えた。まだまだ人生は続く。「楽しい!」と思えることを、たくさん増やしていきたい。
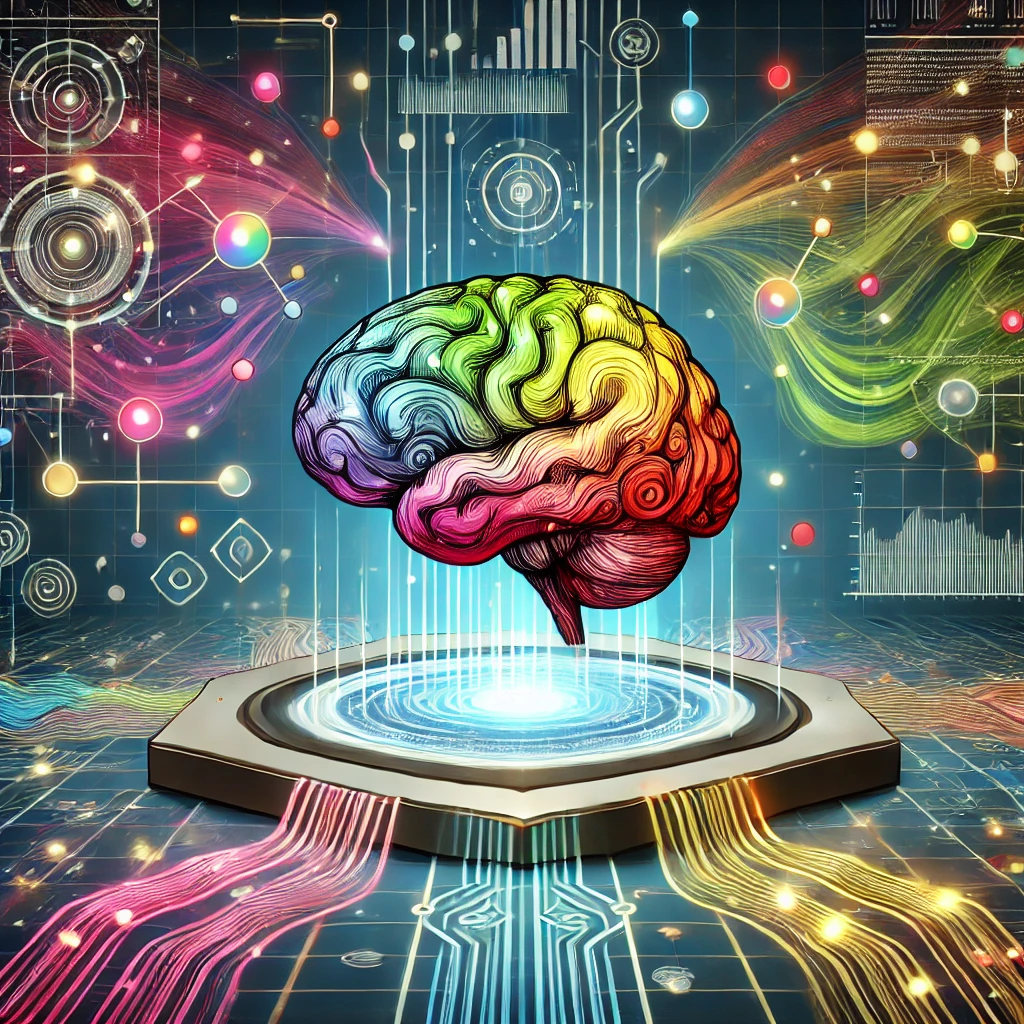
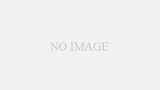

コメント